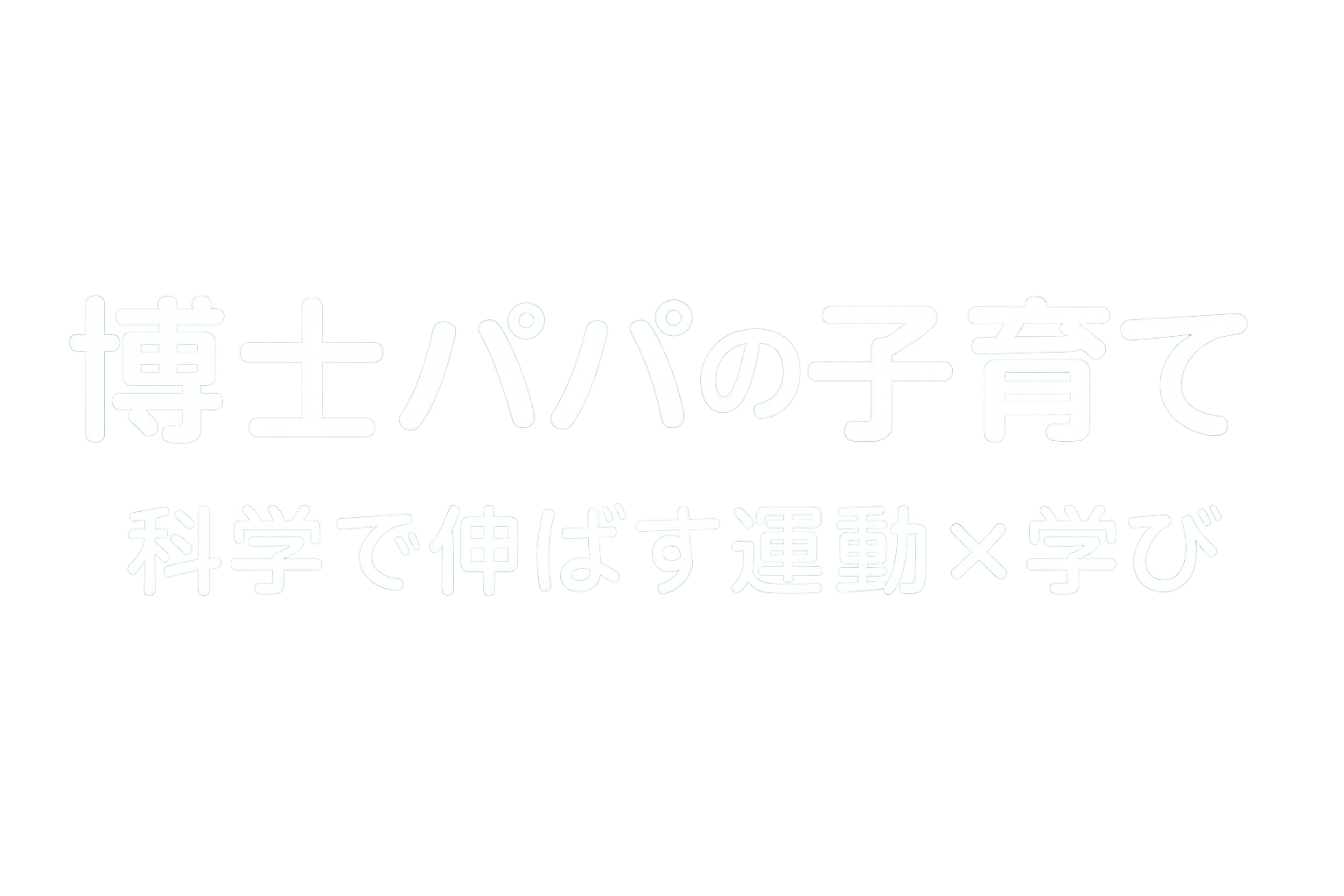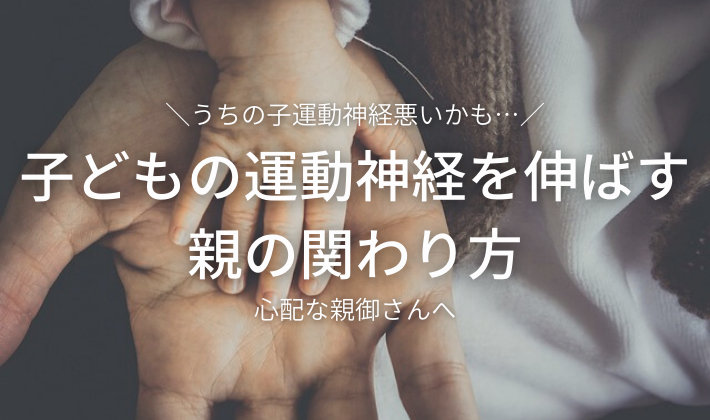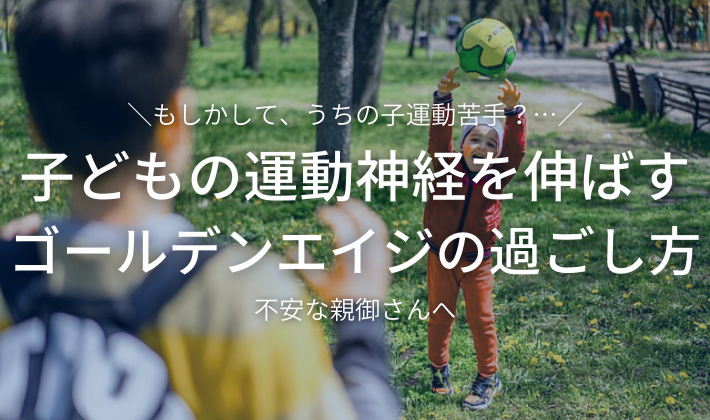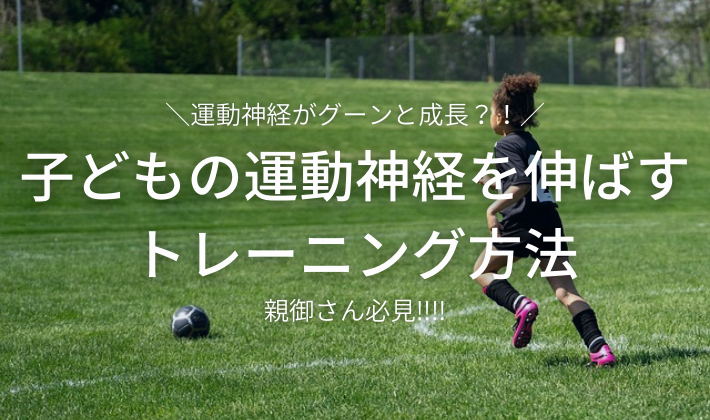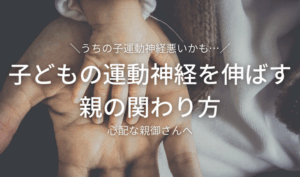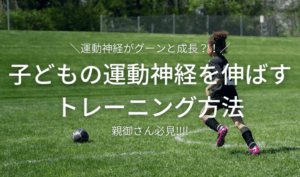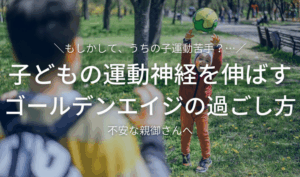・うちの子、運動神経悪いかも
・子どもに少しでも運動に興味を持ってほしい
・運動神経を伸ばすには運動させればいいんじゃないの?
・運動神経を伸ばすための親の関わり方を知りたい
本記事は、上記のお悩み・心配・疑問を解決するために書きました。
こんにちは。シマムーといいます。
普段は3児のパパ&理学療法士として15年以上働いています。
この記事を書いた人

■シマムー
✓博士パパの子育てブログ運営者
✓3児のパパ/理学療法士/スポーツ健康科学修士
✓イングランド&日本サッカー協会指導者資格保持(Lv1/C級)
✓子どもの運動と学びを論文と実践をベースに情報発信中
子どもの運動神経を伸ばしたいからと、習い事を始めさせるご家庭も多いですよね。
でも実は、その前に“親の関わり方”次第で、子どもの伸びしろが大きく変わるって知ってますか?
「うちの子運動苦手かも…」という人は、ぜひ子どもへの関わり方を変えてみてください。
「子どもの運動神経をもっと伸ばしてあげたい!」という人は、子どもへの関わり方から見直してみてください。
本記事の内容を実践すれば、子どもの運動神経を伸ばすための親の関わり方が身につくはずですよ!
運動神経とは

ここでの「運動神経」とは、運動が得意であったり、思い通りに身体を動かせる力のことです。
「運動神経を伸ばしたほうがいい」というのは、多くの方が何となく感じていることかもしれません。
では実際に、運動神経を伸ばすことでどんなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、論文をもとに解説していきますよ。
なぜ運動神経を伸ばすことが大切なのか
文部科学省(2005)の調査によると、その理由は単に「運動が得意になる」だけでなく、体力の向上や体力低下の予防につながることが報告されています。
また、Borerら(2005)やGunterら(2008)は、発育期に欠かせない骨の強化にも重要な役割を果たすとしています。
さらに、運動は学びの面にも良い影響を与えることが分かっています。(Field, 2001、Coe, 2006)
実際に、普段からよく運動をしている子どもほど学業成績が高い傾向があり、20mシャトルランの成績と読解力・算数の得点には相関関係があることも報告されています。(Castelli, 2007)
加えて、運動能力が高い幼児は心理的にもプラスの影響を受けやすいとされています。(杉原, 2010)
特に、運動遊びを通して「自分はできる」という有能感を得た子どもは、日常生活でも自信をもち、積極的に物事に取り組む姿勢を見せるようになりやすいです。(杉原, 1988)
 博士パパ
博士パパ運動神経を伸ばすことは、学力や心理面にも効果的なんですね。
運動神経を伸ばす3つの要素


親の関わり方
子どもの運動能力は、昭和60年ごろを境に低下してきていると言われています。
中央教育審議会(2002)の調査では、その大きな理由として「親の意識」を挙げています。実際、昔に比べて親が子どもの運動に関わる機会が少なくなってきています。
原田(2006)の報告でも、子どもが運動習慣を身につけるかどうかは、親の考えが大きく影響していることが分かっていて、地域の特性や環境、住宅形態といった要素はあまり関係がないとされています。
このことからも、子どもの運動に親の意識が大きく関わっていることが伺えます。



子どもの運動神経を伸ばせるかは、親の意識次第なんです!
ゴールデンエイジ
ゴールデンエイジの過ごし方については、下記の記事で詳しく解説しています。
トレーニング
運動神経を伸ばすトレーニングについては、下記の記事で詳しく解説しています。
この記事では3つの要素のうち「親の関わり方」にフォーカスしてきます。
では、親の関わり方のポイントを論文をもとに紹介していきます。
「親の関わり方」4つのポイント


好奇心を刺激する
子どもの「遊び込みの深さ」と「好奇心・探求心」には関係があると報告されています。(角谷, 2015)
また、別の研究では「好奇心」が運動能力に大きな影響を与えることも報告されており、さまざまなことに興味を持ち挑戦することで好奇心は育ち、運動能力とともに伸びていくとされています。(後藤, 2019)
杉原ら(2010)は、楽しく体を動かしたり、できた!という達成感を重ねることで「運動有能感(自分はできるという感覚)」が育ち、自信を持てるようになることを報告しています。
そうすることで積極性が高まり、さらに運動が好きになって、運動の機会も増え、発達が促されていくと述べています。
以上ことからも、子どもの好奇心を刺激し、楽しく運動ができるということはとても重要なことなんです。



親が好奇心を刺激する環境作りをしてあげることも大事です。
その子に応じた段階を踏む
荒井ら(2013)によると、子どもが運動に取り組むには、「やってみたい」「自分にもできそう」という気持ちが必要であると報告されています。
また朝岡ら(2005)の研究によると、子どもがまだ経験のない動きをするとき、これまでの運動経験をもとに頭の中でイメージし、「できそう」と感じれば挑戦につながります。
逆に「怖い」「痛い」といった感情が先に立つと、最初からやろうとしないことが分かっています。
つまり、その運動に「なじみのある動き」を感じられると子どもは挑戦しやすく、逆になじみのない動きだと「やってみよう」という気持ちが起こりにくいのです。(宮内, 2016)
例えば、「1mの高さからのジャンプ」に取り組む場合、「①地面でジャンプをしてみる、②1mの高さのある場所を歩いてみる、③50㎝の高さからジャンプしてみる」の様に運動を細分化して取り組めると、動作を獲得しやすいです。



気合と根性で運動を克服させようとするやり方は逆効果です。
親の言葉がけ
宮内ら(2016)は、小学校に入ると、運動の出来栄えが意識されるようになり、思うように身体を動かすことができない子どもは「自分は運動が苦手だ」と感じやすくなることを報告しています。
就学前から小学校期にかけての体験は、その後の「運動生活」を大きく左右する大切な時期といえ、(金子, 2005)
実際に、運動の好き嫌いは小学校期に決まることが多いとされています(福富, 2011)
このことからも、子どもの運動に対しては「うまくできたかどうか」を評価する言葉ではなく、「挑戦したこと」や「頑張って取り組んでいる姿勢」に注目して言葉をかけることが大切です。



このような言葉がけすることで運動への動機づけにもなります。
また他の研究では、運動が嫌いになる背景には「運動有能感(自分はできるという感覚)」の欠如があると指摘されています。(岡澤, 2003)
逆に、「運動神経いいね!」など肯定的な声かけを多く受けた子どもは運動有能感が高まり、運動に前向きな気持ちを持ちやすくなると報告されてます。(松井, 2014)
親の過ごし方
子どもの運動や身体活動には、親の影響が大きく関わっています。(ベネッセ教育研究開発センター, 2009、Xu, 2015)
Erikssonら(2008)によると、特に母親が積極的にスポーツや運動を楽しむ家庭では、子どもの運動参加率が高くなる傾向があると報告しています。
また、父親の育児参加も重要です。矢野ら(2024)は、休日に1時間以上子どもと過ごすなど、父親が育児に関わる時間が多いと、親子での運動遊びへの興味や、子どもの運動に対する意欲が高まる可能性を示唆しています。
さらに、Katoらのレビューによると、母親が父親の育児参加を認識している場合、子どもの健康や発達にプラスの影響を与えることも報告されています。



子どもがスマホやテレビばかり観ているのも親の影響が大きいです。
メディアとの付き合い方については、下記の記事で詳しく解説しています。
実践する前に知っておくべき注意点4つ


子どもの好きなこと
林ら(2018)は、幼児は本来、体を動かしたいという「身体活動欲求」がとても高く、その欲求の大きさに比例して運動能力や「自分はできる」という運動有能感も育ちやすくなると報告しています。
そのため、幼児期の運動習得では、まず子どもが興味を持つことや好きなことを尊重し、その中で成功体験を重ねることが大切とされています。(宮内, 2016)
杉原ら(2010)は、実際に楽しい遊びの形で運動を経験することが、運動発達に最も効果的だと報告しています。
さらに、親や指導者は、子どもが自ら「やってみたい」と思う遊びを工夫できるような環境を整えてあげることも重要で、(後藤, 2019)子どもが興味を持って挑戦できる遊びを提供することが、運動能力や意欲の育成につながります。(宮内, 2016)
子どもの興味・関心・好きなことを知ることができたら、運動と結び付けてあげることが大事です。



まず、子どもの好奇心を刺激するものを知りましょう!
子どもの運動レベル
子どもの運動は、本来繰り返していくうちに少しずつ上手になり、段階的に能力が高まっていくものです。
しかし、特に幼児期の子どもは集中力が続きにくく、常に新しいことに興味が移りやすい特徴があります。
成功した運動は繰り返しますが、失敗するとすぐにやめて別の運動に移ることも少なくありません。(宮内, 2016)
子どもの持つ運動レベルと実践する運動レベルのギャップが大きすぎると、子どもはその運動をしようとしません。
だからこそ、親は子どもの現在の運動レベルを正しく理解することが大事なんです。



子どもの身体機能レベルを知ると、運動レベルを把握しやすいです。
子どもの身体機能レベルチェックについては、下記の記事で詳しく解説しています。
目標設定の重要性
三井ら(2013)は、子どもの運動指導では、「子どもがどの運動レベルにいるか」を理解し、「どんな運動を身につけたいのか」という目的に合わせて進めることが大事になってくると報告しています。
ですので、運動の目標は子どものレベルに応じていくつかの段階に分けてあげるといいです。そして、1つ出来たら次の段階へ進んでいきましょう。
別の研究でも、最終的に目指す動きをいきなりやらせるのではなく、その動きに似た簡単な動きをしたり、段階的に動きを運動に取り入れることが効果的だということが明らかになっています。(宮内, 2016)
目標設定がずれていると、運動への意欲も続かないので注意が必要です。
子どもの年齢によってゴールデンエイジの過ごし方とすり合わせて、時期とレベルごとに目標設定することが理想的です。



「やってみたい」「自分にもできそう」と思える目標レベルが良いです。
運動嫌いになる原因
運動好きになってほしいという前に、「運動嫌いにならないためには?」を知ることも大切です。
小学校に入ると、運動の目標や出来栄えが意図的・計画的に意識されるようになります。そのため、運動ができない子どもは苦手意識が生まれやすくなります。(宮内, 2016)
特に、小学校年代では「速い・遅い」「できる・できない」といった比較や、恐怖心を伴う運動が、運動嫌いになる原因になりやすいとされています。(福富, 2011)
他の研究によると、運動が不得意な子どもは…
- みんなで運動しているとき
- 上手な子と一緒に運動しているとき
- 勝ち負けにこだわる子と運動しているとき
上記に抵抗感を持ちやすく、さらに大人や友達から「上手にできないこと」を注意されると、運動そのものが嫌いになってしまうリスクがあることが報告されています。(中野, 2019、伊藤, 2024)



運動が不得意な子は運動を教えてもらい交流することで楽しさを感じやすいです。
我が家での実践例


子どもの好きをどのように運動へ結び付けていくかを、我が家を例にしてフェイズごとの目標を掲げ、順序立てて解説していきますね!
1. 好奇心のきっかけを大事にする
たまたま日曜の朝に観た「ゲゲゲの鬼太郎」 に夢中になっていると気づきました。
我が家の場合、子どもの興味と運動を結び付けた結果「妖怪ごっこ」が始まりました。
ちなみにパパは悪い方の妖怪役に(笑)。
それからは、ただアニメを観るだけでなく、遊びを通して身体を動かす時間を増やしていきます。
キッカケは何でも良いと思います。子どもは毎日必ず何かに興味を持ちます。
とにかく子どもの好奇心のサインを見逃さないことが大事です。



妖怪ごっこでは、協力し合えば悪い妖怪を退治できるという成功体験も大事にしてます。
2. 好きを作品や表現に広げる
子どもの「好き」を運動以外の切り口からも広げていくことで、さらに好奇心を刺激していきます。
我が家の場合、保育園や家で鬼太郎や猫娘たちの絵を描いたり、工作でアイテムをつくるように。
また、子どもが好きなものを何らかの形で自ら表現した時に大人が関心を持つことで、自然と活動の幅が広がります。
言葉がけ以外の関心を表現する方法として、子どもの作品を展示したり、スマホの待受画面にしたりする方法も子どもに伝わりやすいと思いますよ。



親も子どもの世界観にどっぷりと浸かってみてください。
3. 興味を“次のチャレンジ”につなげる
いくつかの共通点を頼りに、鬼太郎の流れから「アニメ鬼滅の刃」へ広げていきました。
鬼滅の刃の方が運動能力の高いキャラクターも多いことから、同じように身体を動かすことへの興味も湧いてきます。
我が家では、アニメを観ながら「伊之助と同じことできるかな?」と子どもの興味を刺激してトランポリンやアスレチックで親も一緒に身体を動かしていました。
感覚としては、ビリーズブートキャンプならぬ、鬼滅のキャラクターキャンプといった感じです。
また、新たに表現の幅も広がることで、自宅では日輪刀や禰豆子の口枷などのアイテムをつくり始めました。
親が「パパも禰豆子になりたい」「どうやって作ったの?」と関わることで、子どもの好奇心はどんどん膨らみます。
いつしか妖怪ごっこは「鬼殺隊ごっこ」へ。もちろん鬼はパパです(笑)。



子どもと友達目線で楽しみましょう!
4. ごっこ遊びが身体活動に発展
この頃には身体を動かすこと自体が好きになっています。
走る、飛ぶ、転がる…気づけばソファーや椅子からジャンプ、布団の上を駆け回る日常に。
それだけでは物足りない彼女たちにとって、家でのトランポリンやアスレチックは効果抜群です。
運動の幅を広げるために場所を変えて公園の遊具を使った鬼殺隊ごっごや、屋内外キッズパークでのアクティブな遊びにも発展させました。
場所を変える場合、はじめは運動内容まで大きく変える必要はありません。
むしろ、場になれるためにも、子どもが慣れ親しんだ運動を取り入れた方が良い場合もあります。
子どもの様子を見ながら判断してあげましょう。



外出が難しい場合、自宅の中で使える遊具を導入してみるのもアリです。
5. 実体験とリンクさせる
実体験を積ませてあげたいと考え、忍者コスプレをレンタルし日光江戸村へ。
実際に当時の町を歩いたり、忍者や侍、花魁に会ったり、忍者修行したり。
アニメの世界観が“現実の体験”へと変わることは、子どもたちにとって相当な衝撃だったようです。
その結果、この日を境に、長女の走り方が忍者走りになりました(笑)。
好奇心→ごっこ遊び→屋外遊び→実体験という流れを踏まずに、いきなり日光江戸村へ遊びに行っていたら、うちの子は忍者を怖がっていたでしょう。
またこの頃から、アニメ関係なくアクロバティックな動きや運動を「少し怖いけどやってみたい」と興味を持つようになります。



今までやろうともしなかった高所からのジャンプもお手の物に!
6. 新しい運動への興味
最近は、自宅や公園以外の場所で遊ぶことにも慣れてきて、キッズパークで体験したボルダリングに興味を持ち始めてます。
今後、子どものレベルに合わせて体験教室に挑戦してみてもいいなと思ってます。
また、公園での「走る、飛ぶ、転がる」といった自由な遊びは変わらず大好きなので、その動きに近いパルクールの動画を一緒に観て興味を刺激したり、挑戦しても楽しめるかなと考えてます。
子どもの好奇心が、自然と 体を使う活動 → 新しい運動 へとつながっているんですね。
ただし、興味を持ち始めたからといって「習い事へ全投げ」するのは環境もガラッと変わるため、おススメしません。
子どもに合わせて、徐々に馴染ませていきましょう。



親だからこそできる関わり方を大事にしてほしいです!
運動神経を伸ばす親の関わり方まとめ


子どもの運動神経の伸びしろは、良くも悪くも“親の関わり方”で決まってくる部分が大きいんです。
もしあなたが、お子さんの力をできるだけ引き出してあげたいと思うなら、この記事で紹介した“運動をさせる前にできること”から実践してみてください。
子どもの好奇心は、運動の入り口になります。
子どもの「好き」をみつけたら、意識して運動と結びつけてあげてください。
そうすることで、好奇心は自然と動き出します。
その上で「面白いね」「一緒にやってみよう」と親が積極的に関わることで、好奇心は連鎖していき、運動・表現・学びへと広がります。



なによりも、まず親の意識とそれに伴った関わり方が大切なんです。
最後までご覧いただきありがとうございました!
ご意見やご質問、気になる点等あれば、問い合わせフォームからご連絡ください。
参考文献:
文部科学省 (2005). 平成17年度体力・運動能力調査報告書. 東京: 文部科学省.
中央教育審議会 (2002). 子どもの体力向上のための総合的な方策について(答申). 東京: 文部科学省.
ベネッセ教育研究開発センター (2009). 子どものスポーツ・芸術・学習活動データブック. 岡山: ベネッセコーポレーション.
杉原 隆, 吉田 伊津美, 森 司朗, 筒井 清次郎, 鈴木 康弘, 中本 浩揮, & 近藤 充夫 (2010). 幼児の運動能力と運動指導ならびに性格との関係. 体育の科学, 60(5), 341–347.
杉原 隆 (1988). 幼児の運動遊びに関する有能さの認知とパーソナリティの関係. 体育学研究, 30(1), 25–35.
原田 正文 (2006). 子育ての変貌と次世代育成支援. 名古屋: 名古屋大学出版会.
角谷 詩織, 梅川 智子, 渡邉 典子, & 亀山 亨 (2015). 幼児期の遊びへの関わり方の違いとその影響-自己調整力,好奇心探究心,表現力を中心に-. 第57回総会発表論文集, 179.
後藤 千穂, 春日 晃章, 中野 貴博, & 小椋 優作 (2019). 幼児期の体力・運動能力と性格特性主要5要因との複合的関連. 教育医学, 64(3), 226–232.
荒井 迪夫, & 中西 一弘 (2013). 幼児体育指導者の動感認識に関する一考察. 淑徳短期大学研究紀要, 52, 61–70.
朝岡 正雄 (2005). 動きの模倣とイメージトレーニング. バイオメカニズム学会誌, 29(1), 31–35.
宮内 孝 (2016). 幼児の基本的な動きを身につける運動指導のあり方. Journal of The Human Development Research, 6, 23–30.
金子 明友 (2005). 身体知の形成. 東京: 明和出版.
福冨 恵介, 春日 晃章, & 篠田 知之 (2011). 大学生の運動・スポーツおよび保健体育の授業に対する好き嫌いに影響を及ぼす時期. 教育医学, 57(2), 205–212.
岡澤 祥訓 (2003). 運動好きと自己有能感. 体育の科学, 53(12), 905–909.
松井 幸太 (2014). 高校運動部活動における生徒の内発的動機づけ―指導者のフィードバック行動および生徒と指導者の関係に対する生徒の認知からの検討―. スポーツ心理学研究, 41(1), 51–63.
矢野 真理 (2024). 父親の養育行動が家庭での親子の身体活動に及ぼす影響―子育て時間に注目して―. 神戸女子短期大学論攷, 69, 13–23.
加藤 継彦, 越智 真奈美, 加地 裕子, 須藤 舞子, 大塚 美也子, & 竹原 健二 (2024). 父親の子育て参加が母親・子ども・父親に及ぼす影響に関するレビュー. 日本公衆衛生学会.
林 貢一郎 (2018). 幼児における運動能力と運動に対する意識の関連性およびその性差. 國學院大學人間開発学研究, 9.
三井 登 (2013). 幼児期の運動遊びにおける指導法の課題. 帯広大谷短期大学紀要, 50, 127–136.
中野 貴博 (2019). 運動の得意苦手,好き嫌いによる楽しさを感じる瞬間の違い~運動があまり得意でない児童の心理特性~. 子どもと発育発達, 16(1), 25–29.
伊藤 奨, 曽我 啓史, & 加藤 孝基 (2024). いわゆる「運動神経の良し悪し」に関わる要因の解明. 南山大学紀要『アカデミア』人文・自然科学編, 28, 159–181.
Borer, K. T. (2005). Physical activity in the prevention and amelioration of osteoporosis in women: Interaction of mechanical, hormonal and dietary factors. Sports Medicine, 35(9), 779–830.
Gunter, K., Baxter-Jones, A. D., Mirwald, R. L., Almstedt, H., Fuchs, R. K., Durski, S., & Snow, C. (2008). Impact exercise increases BMC during growth: An 8-year longitudinal study. Journal of Bone and Mineral Research, 23, 986–993.
Field, T., Diego, M., & Sanders, C. E. (2001). Exercise is positively related to adolescents’ relationships and academics. Adolescence, 36, 105–110.
Coe, D. P., Pivarnik, J. M., Womack, C. J., Reeves, M. J., & Malina, R. M. (2006). Effect of physical education and activity levels on academic achievement in children. Medicine & Science in Sports and Exercise, 38, 1515–1519.
Castelli, D. M., Hillman, C., Buck, S. M., & Erwin, H. E. (2007). Physical fitness and academic achievement in third-fifth-grade students. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29, 239–252.
Xu, H., Wen, L. M., & Rissel, C. (2015). Associations of parental influences with physical activity and screen time among young children: A systematic review. Journal of Obesity, 2015, 1–23.
Eriksson, M., Nordqvist, T., & Rasmussen, F. (2008). Associations between parents’ and 12-year-old children’s sport and vigorous activity: The role of self-esteem and athletic competence. Journal of Physical Activity and Health, 5, 359–373.