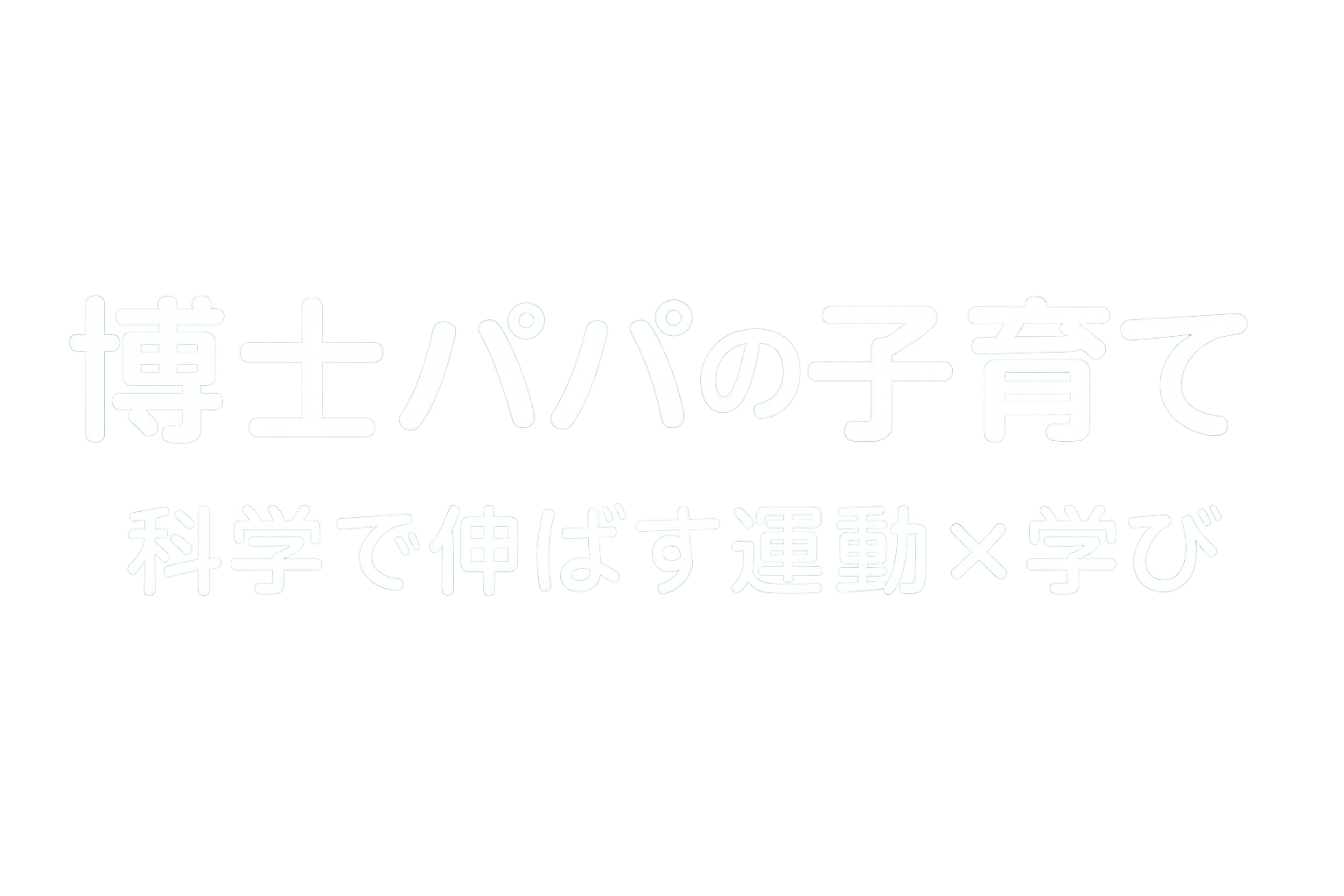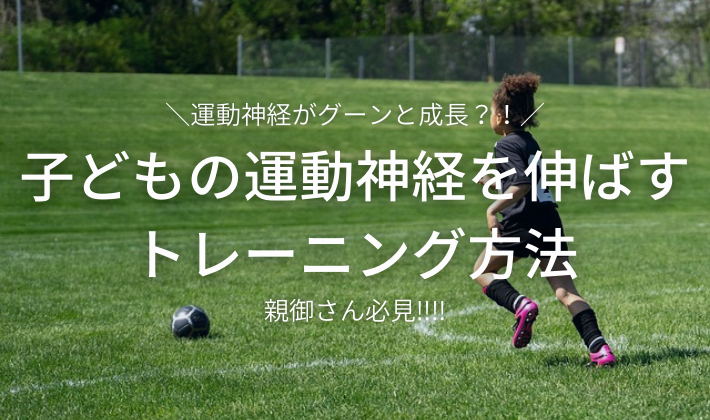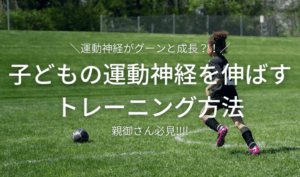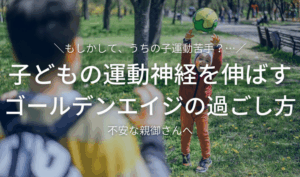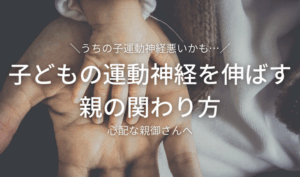・うちの子、運動神経悪いかも
・運動神経伸ばすには運動させればいいんじゃないの?
・そもそも親の関わり方で運動神経って良くなるの?
・運動神経を伸ばすための親の関わり方を知りたい
本記事は、上記のお悩み・心配・疑問を解決するために書きました。
こんにちは。シマムーといいます。
普段は3児のパパ&理学療法士として15年以上働いています。
この記事を書いた人

■シマムー
✓博士パパの子育てブログ運営者
✓3児のパパ/理学療法士/スポーツ健康科学修士
✓イングランド&日本サッカー協会指導者資格保持(Lv1/C級)
✓子どもの運動と学びを論文と実践をベースに情報発信中
子どもの運動神経がよくなってほしいと思うばかりに、とりあえず習い事をさせる親多いですよね。
でも、習い事をさせてるからといって誰でも運動神経が飛躍的に伸びるかというとそうでもないです。
運動する前段階として親の関わり方がしっかりしてないと伸びるものも伸びません。
「うちの子運動苦手かも…」という人は、ぜひ子どもへの関わり方を変えてみてください。
「子どもの運動神経をもっと伸ばしてあげたい!」という人は、子どもへの関わり方から見直してみてください。
本記事の内容を実践すれば、子どもの運動神経を伸ばすための親の関わり方が身につくはずですよ!
運動神経とは
ここでいう「運動神経」とは、ざっくり言えば 運動能力 を指します。
つまり、運動が得意であったり、自分の思い通りに身体を動かせる力のことです。
「運動神経は伸ばせたほうがいい」というのは、多くの方が何となく感じていることかもしれません。
では実際に、運動神経を伸ばすことでどんなメリットが得られるのでしょうか。ここからは、論文をもとに具体的に見ていきましょう。
なぜ運動神経を伸ばすことが大切なのか
その理由は、単に運動が得意になることだけではありません。
まず、運動を習慣的に行うことで 体力の向上や体力低下の予防 につながります。(21また、発育期に欠かせない 骨の強化 にも重要な役割を果たします。(4,12
さらに、運動は学びの面にもプラスの影響を与えることが分かっています。い(11,7普段からよく運動をしている児童・生徒は 学業成績が良い という研究があり、実際に 20mシャトルランの成績と読解力・算数学力の得点には相関関係 が示されています。(5
加えて、運動能力の高い幼児は心理的にも良い影響を受けやすいことが報告されています。(35特に、運動遊びを通して 有能感(自分はできるという感覚) を得た子どもは、日常生活でも自信をもち、積極的に物事に取り組む傾向があります。(34
つまり、運動は身体機能の向上だけでなく、学力や心理面にも効果をもたらす ことが期待できるのです。
運動神経を伸ばす3つの要素
ゴールデンエイジ
人間が基本的な運動を身につける上で最も適した時期のひとつである「黄金時代」と呼ばれる貴重な時期
9歳頃からはじまり、大人になってからではなかなかうまく覚えられないような動きもこの時期にはあっという間に覚えてしまい、一度身につくとなかなか失われないという特性を持っています。
詳細は「運動神経を伸ばすためのゴールデンエイジの過ごし方」の記事で
トレーニング
幼児の足の指の力は「歩く」「走る」「跳ぶ」といった運動能力に関係することが分かっています。その足の機能は幼児期に形成されると言われていて、足の裏や足の指を使った走るなどの基礎的な運動が可能になるのも幼児期です。
また学童期の運動能力にも足の指や足の裏のアーチが関係していることが分かっています。
詳細は「運動神経を伸ばすための足部のトレーニング方法」の記事で
幼児期の足指や体幹の力は、様々な運動能力に関係することが分かっています。学童期の足指の動きまでもが運動能力に関係していたり、体幹筋力は運動だけでなく、学力向上にも関与している可能性があるんです。
親の関わり方
昭和60年頃を境に、子どもの運動能力は低下してきているといわれています。
その大きな要因のひとつが「親の意識」であり、実際、我が子の運動に対する関わりが以前に比べて薄くなってきているようです。(6
研究でも、親の考え方や意識が子どもの運動習慣に強く関係していることは明らかになっています。一方で、地域の特性や住環境、住宅形態といった一見影響しそうな要因とは関係がないとされているのです。(13
つまり、親の運動歴や環境に関わらず、親の意識次第で子どもの運動神経は大きく伸ばせる ということです。
では具体的に、どんな関わり方をすればいいのでしょうか。ここでは、今日からすぐに実践できる方法を紹介していきます。
運動神経を伸ばすための親の関わり方とは?
好奇心をくすぐる
遊び込み度と好奇心や探求心の間には関連性がある(幼児期の体力・運動能力と性格特性~(6
楽しく運動したり達成経験を得る中で運動有能感を獲得し自分に自信を持つことで積極性が増すとともに運動好きになって運動機会が増え発達が促進される((幼児期の体力・運動能力と性格特性~(25
好奇心が運動能力に強く影響する。そのことで様々なことに興味・関心を持ち取り組む中で好奇心はますます強まり、運動能力とともに高まる((幼児期の体力・運動能力と性格特性~
親や運動指導者は、子どもが好奇心を持って自ら遊びに向かったり、遊びを工夫するような環境を整えてあげることが大切((幼児期の体力・運動能力と性格特性~
子どもが「やってみたい」と思うような遊びを提供することの重要性((幼児期の基本的な動き
その子に応じた段階設定
子どもは「やってみたい」「自分にできそうだ」という気持ちが生じないと運動をしようとしない((幼児期の基本的な動き(荒井1-62
子どもはまだやったことのない運動の動きをを「今持っている有効な運動経験」を引き合いに出してきて動きを理解しようとする。それからその未知の運動をやるときの感じを頭の中でやってみる。そこで成功すれば「できそうな気がする」に移行するし、「怖い」「痛い」といった感情が先立てば最初からやってみようとも思わない((幼児期の基本的な動き(朝岡2-33
流れとして「わかるような気がして→できるような気がして→実際にやってみる」ということだ((幼児期の基本的な動き
その運動に「なじみのある動き」を感じることでやってみようという気持ちになりやすいし、逆になじみのない動きはやってみようとなづらい((幼児期の基本的な動き
親の言葉がけ
動きの出来栄えの評価は気にしない。小学校に入学すると、目標とする動きの出来栄えが意図的・計画的になることで運動ができない子どもは運動への苦手意識を持つようになる((幼児期の基本的な動き
よって就学前のスポーツ運動がその子供の運動生活を左右する重要な時期にもなりうる((幼児期の基本的な動き(金子5-37
運動・スポーツ嫌いの原因が「運動有能感」の欠如であると指摘されている((大学生の運動・スポーツおよび保健体育(9
運動・スポーツの好き嫌いは小学校期に決まるこが多く、次いで幼少期と中学校期((大学生の運動・スポーツおよび保健体育
親の過ごし方
親の身体活動量は子どもの身体活動量と関係する(2
母親自身がスポーツ活動を好む方が子どものスポーツ活動率が高くなる(10
休日の父親の子育て時間が1時間以上か未満かが、親子での運動遊びへの興味を親が持っているかどうかの境目にもなり、より多くの育児に父親が参加している場合、子どもの運動嗜好性が高まる可能性がある(父親の養育行動が…
実践する前に知っておくべき注意点4つ
子どもの好きなこと
本来、子ども(特に幼児)は身体活動欲求(体を動かしたい欲求)が高く、その欲求に比例して運動能力と運動有能感も高くなる((幼児における運動能力と運動に対する意識
子どもの運動レベル
目標設定の重要性
子どもにどのような力をつけたいのかという目的下、状況との関係で指導を展開していく((幼児期の基本的な動き(三井9-127
最終目標である運動をいきなり子供たちにやらせるのではなく、最終目標とする動きと類似する動きを用いることの重要性((幼児期の基本的な動き
運動嫌いになる原因
小学校に入学すると、目標とする動きの出来栄えが意図的・計画的になることで運動ができない子どもは運動への苦手意識を持つようになる((幼児期の基本的な動き
小学校年代で「速い」「遅い」や「できる」「できない」を他者に知られたり、比較されたりすることや恐怖感の伴う運動種目が運動嫌いになる原因((大学生の運動・スポーツおよび保健体育
我が家での実践例
楽しいを感じてもらう
特に幼児期の子どもの運動習得には、子どもの興味・関心や成功体験が大きく影響する。((幼児期の基本的な動き
遊びの形での運動経験が運動発達に最も有効((幼児期の基本的な動き(杉原21-343
親も子どもの世界観の中へ
親や運動指導者は、子どもが好奇心を持って自ら遊びに向かったり、遊びを工夫するような環境を整えてあげることが大切((幼児期の体力・運動能力と性格特性~
子どもが「やってみたい」と思うような遊びを提供することの重要性((幼児期の基本的な動き
親から誘ってみる
子どもの気持ちを尊重
本来子どもの運動は繰り返していくうちに徐々に洗練され、段階的に高まっていくものだが、特に幼児期の子どもは集中力に乏しく常に新しいものに興味・関心が移行する。また、成功した運動には繰り返し取り組むが、失敗するとその運動をやめて他の運動に移行することも多い((幼児期の基本的な動き